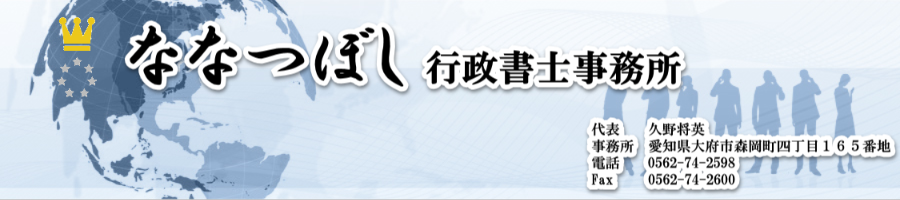
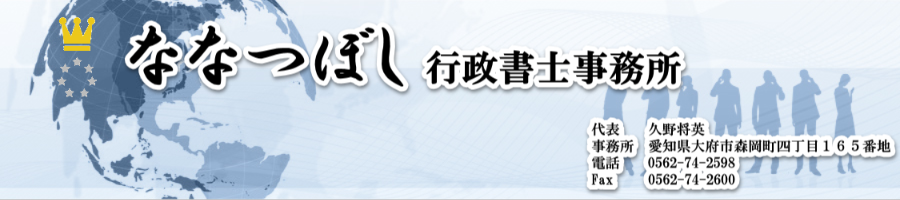
父母の離婚後等の子の養育に関する見直し(公布から2年以内に施行予定)
婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して負う責務を明確化
第817条の12
1父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
2父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。
親権が子の利益のために行使されなければならないものであることを明確化
第818条
1親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
ⅰ養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
ⅱ子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
離婚後の親権者に関する規律を見直し
第819条
1父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
2裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
3子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
4父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
5第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
7裁判所は、第2項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
ⅰ父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
ⅱ父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第1項、第3項又は第4項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
8第6項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
協議離婚の際は、父母の協議により父母双方又は一方を親権者と指定することができる。
協議が調わない場合、裁判所は、子の利益の観点から、父母双方又は一方を親権者と指定する。
婚姻中を含めた親権行使に関する規律を整備
第824条の2
1親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
ⅰその一方のみが親権者であるとき。
ⅱ他の一方が親権を行うことができないとき。
ⅲ子の利益のため急迫の事情があるとき。
2父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
3特定の事項に係る親権の行使(第1項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。
父母双方が親権者であるときは共同行使することとしつつ、親権の単独行使が可能な場合を明確化
・子の利益のため急迫の事情があるとき
・監護及び教育に関する日常の行為
監護の分掌に関する規律や、監護者の権利義務に関する規律を整備
第766条
1父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
第824条の3
1第766条(第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第820条から第823条まで【第820条、第821条、第822条、第823条】に規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。
2前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。
養育費債権に先取特権を付与(債務名義がなくても差押え可能に)
第306条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
共益の費用
雇用関係
子の監護の費用
葬式の費用
日用品の供給
第308条の2
子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
第766条及び第766条の3(これらの規定を第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
第877条から第880条までの規定【第877条、第878条、第879条、第880条】による扶養の義務
法定養育費制度を導入(父母の協議等による取決めがない場合にも、養育費請求が可能)
第766条の3
1父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
ⅰ父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
ⅱ子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
ⅲ子が成年に達した日
2離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。
3家庭裁判所は、第766条第2項又は第3項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第1項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる
婚姻中別居の場面における親子交流に関する規律を整備
第817条の13
1第766条(第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。
3家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。
4前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
5前項の定めについての第2項又は第3項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
父母以外の親族(祖父母等)と子との交流に関する規律を整備
第766条の2
1家庭裁判所は、前条第2項又は第3項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第1項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
2前項の定めについての前条第2項又は第3項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
ⅰ父母
ⅱ父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)
養子縁組後の親権者に関する規律の明確化、養子縁組の代諾等に関する規律を整備
第797条
1養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
3第1項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。
4第1項の承諾に係る親権の行使について第824条の2第3項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第1項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第3項の規定による審判をすることができる。
第818条
1親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
ⅰ養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
ⅱ子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
財産分与の請求期間を2年から5年に伸長、考慮要素を明確化
(婚姻中の財産取得・維持に対する寄与の割合を原則2分の1ずつに)
第768条
1協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から5年を経過したときは、この限りでない。
3前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。
夫婦間契約の取消権、裁判離婚の原因等の見直し
第754条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。(削除)
第770条
1夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
ⅰ配偶者に不貞な行為があったとき。
ⅱ配偶者から悪意で遺棄されたとき。
ⅲ配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
ⅳその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2裁判所は、前項第1号から第3号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。